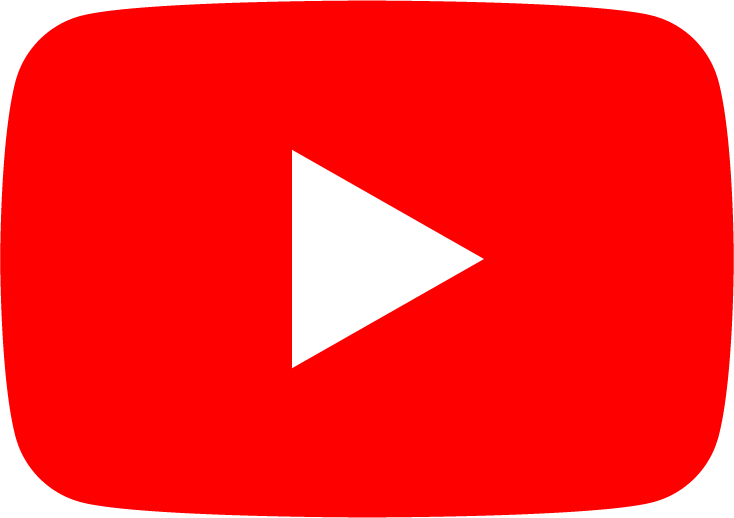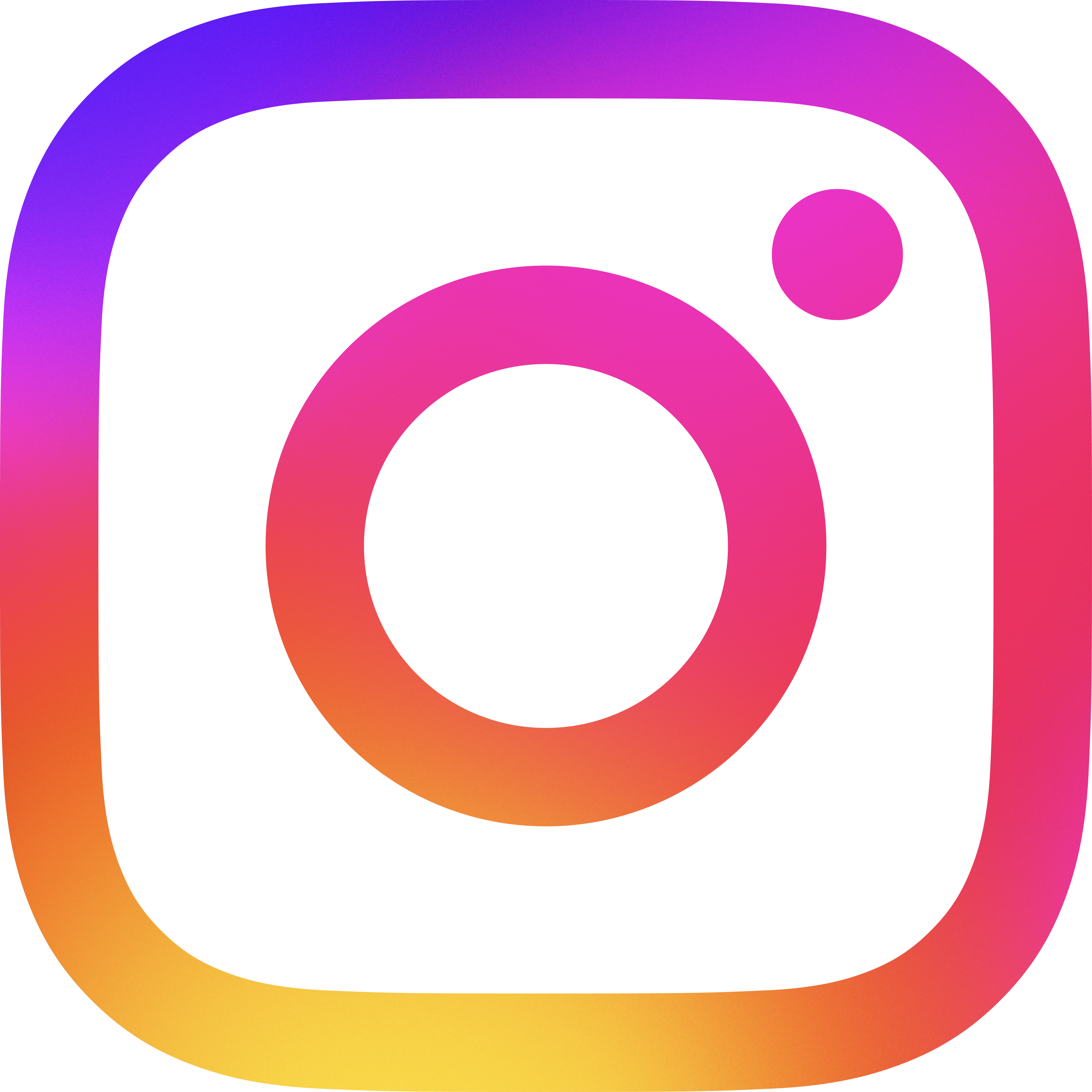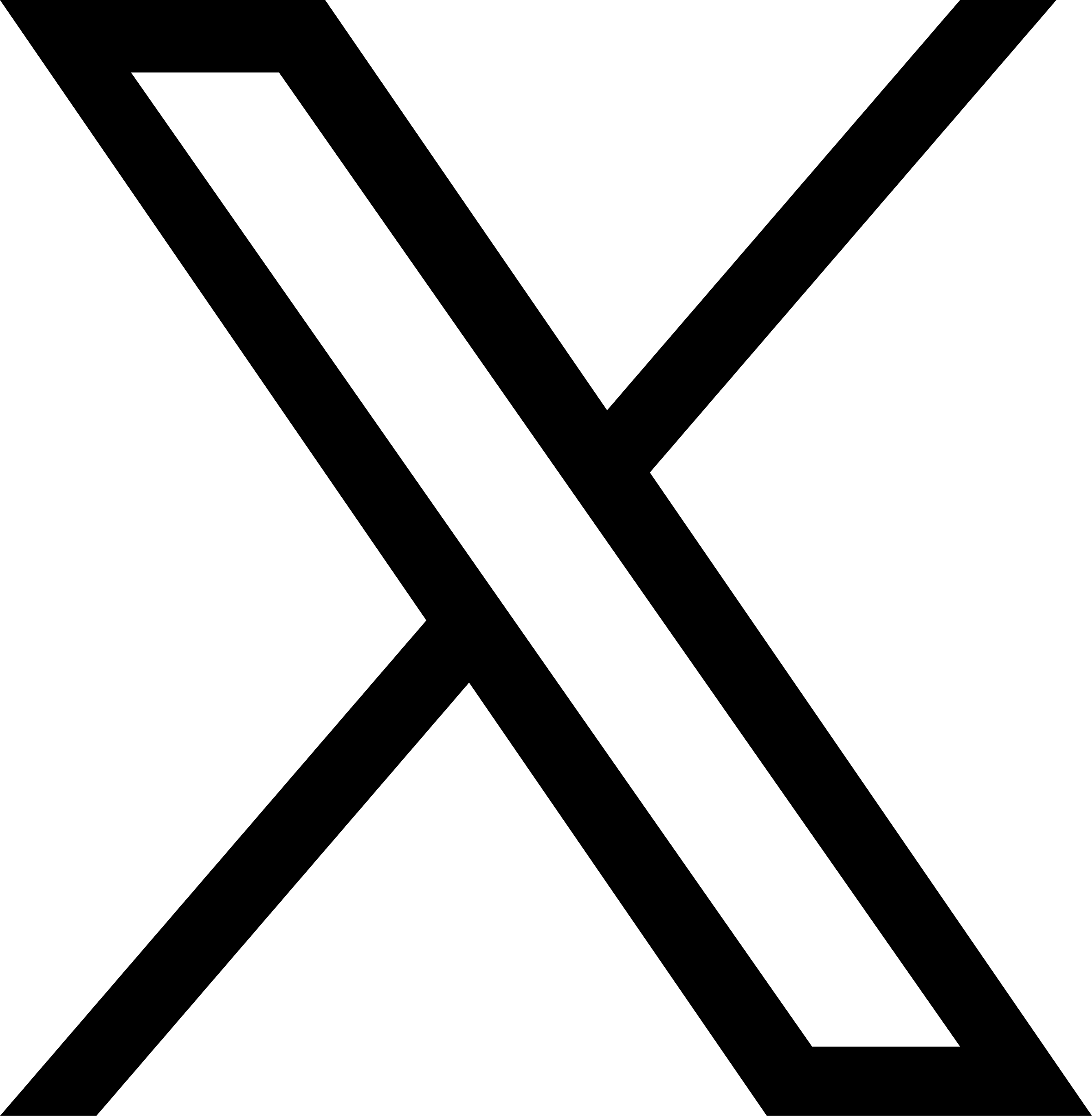高度情報研究教育センター 林 秀彦
報告者 林 秀彦
1.学長の定める重点目標
1-1.教育大学教員としての授業実践
(1)目標・計画
将来,教師を目指す学生に対して,あらゆる課題に多角的に根気強く取組むことができるように,情報教育をとおして情報活用能力を育成する授業実践を展開し,豊かな教育実践力を養成する。授業実践では,特に次の3点において創意工夫する。
- 授業内容:学生のやる気を高めるように学習内容に新規性を持たせる工夫をする。
- 授業方法:プレゼンテーションソフトを効果的に活用し,理解促進を工夫をする。
- 成績評価:実習の評価は課題解決結果のみでなく,その過程も評価できるように実習の作業報告を兼ねたレポートを提出させる。また、学生同士が切磋琢磨できるような評価のしくみを構築したい。
(2)点検・評価
豊かな教育実践力の養成に向けて,情報教育をとおして情報活用能力を育成する授業実践を展開できた。実践情報教育では,特に次の3点において創意工夫した。
- 授業内容:学生が自ら課題を解決できるような新規の課題を設定し,オリジナル教 材によって,情報の収集・加工・分析・生成を効果的に学習できるように工夫した。
- 授業方法:プレゼンテーションソフトやプロジェクタの効果的な活用,オリジナル教材の活用,質問しやすい時間の適宜設定などによって理解促進させる工夫ができた。
- 成績評価:学習過程を省みることができるように実習の報告を兼ねたレポートの提出や,学生同士が切磋琢磨できるように相互評価カードによる評価を実施できた。
1-2.大学教員としての社会(地域)貢献
(1)目標・計画
本学の学生が教員になったときにICT活用による効果的な教育を行えるように情報教育に関する教育・研究活動などをとおして社会貢献する。また,徳島県では「e-とくしま」の推進や普及が進められている。その関連から2008年に開催予定の地域ICT未来フェスタなどの情報通信技術に関するイベントに向けて,情報教育に関わる教育・研究活動の観点から準備することで,地域連携活動の推進を図りたい。
(2)点検・評価
徳島県では「e-とくしま」の推進や普及が進められており,その関連から2008年に開催予定の地域ICT未来フェスタに向けた準備が進められている。9月には関係する講演会に積極的に参加できた。また,準備として検討部会に参加することで地域連携活動の推進を図った。その他,8月には,独立行政法人教員研修センター主催の平成19年度産業・情報技術等指導者養成研修の講師として,情報メディアを用いた情報表現の研修に参画することで社会貢献できた。
2.分野別
2-1.教育・学生生活支援
(1)目標・計画
- 学生がいつでも主体的に授業に取り組めるように,メールシステムを活用して,いつでも質問を受付けることができる授業支援環境を整備する。
- メーリングリストなどによる学習支援によって迅速な情報伝達ができる情報環境を整える。
- 社会性及び実践的能力やコミュニケーション能力を養成するために,少人数の授業では,対話の重視とICT活用をとおして実践的な教育活動を展開したい。
(2)点検・評価
- 学生がいつでも主体的に授業に取り組めるように,メールシステムを活用して,いつでも質問を受付ける授業支援環境を整備した。
- LMSによる学習支援システムを活用して,迅速な情報伝達を実現した。
- 社会性及び実践的能力やコミュニケーション能力を養成するために,少人数の授業では,学生による発表の機会を設けて,質疑応答等の対話を重視する時間を設定できた。また,ICT活用をとおして実践的な教育活動を展開できた。
2-2.研究
(1)目標・計画
- 従来からの研究テーマ(複数属性の評価法)をまとめ,国際会議での発表を通して,世界に研究成果を公表する。
- 横断性の高い研究プロジェクトに参画する際に,専門性を効果的に活かす。
- 学内外の研究助成の公募に積極的に申請し,特に学外資金の調達に重点を置く。
(2)点検・評価
- 従来からの研究テーマ(複数属性の評価法)をまとめ,国際会議での発表3件を通して,世界に研究成果を公表した。また,国際論文誌に1件掲載された。
- 専門性を効果的に活かし,学外の研究プロジェクトに客員特別研究員として参画した。
- 研究助成の応募では,科研費,シーズ発掘試験研究,脳と創造性に関する研究助成の計3件,その他,分担として1件の科研費を申請するなど積極的に申請できた。
2-3.大学運営
(1)目標・計画
大学運営において,センター部における高度情報研究教育センターの果たす役割を認識し,センター所長の業務が効果的に進められるように,しっかりサポートすることで,間接的に本学の運営に貢献する。
(2)点検・評価
大学運営において,センター部における高度情報研究教育センターの果たす役割を認識し,センター所長の業務が効果的に進められるように,しっかりサポートすることで,間接的に本学の運営に貢献した。
2-4.附属学校・社会との連携、国際交流等
(1)目標・計画
- 遠隔授業観察システムの活用をとおして,附属学校園の教員との連携を深めたい。(附属学校)
- 大学と地域・社会との交流・連携を積極的に行い,社会に貢献していきたい。 (社会連携)
- 国際会議に参加して,国際間の交流を積極的に深めていきたい。(国際交流)
(2)点検・評価
- 遠隔授業観察システム活用を技術的にサポートして,附属学校園との連携に協力できた。(附属学校)
- ICT未来フェスタの開催に向けて協力することで,地域・社会との交流・連携を積極的に行い,社会に貢献できた。(社会連携)
- 国際会議にて3件の研究を発表し,国際間の交流を積極的に進めることができた。その他,オーストラリアの大学より依頼のあった博士学位論文の審査に参画できた。また,その際,本学の紹介リーフレットを送付することで,国際交流に貢献できた。(国際交流)
3.本学への総合的貢献(特記事項)
大学院を設置していない大学の教員を通じて,本学を紹介し,学生の充足につなげる貢献ができた。また,鳴門教育大学情報教育ジャーナルのウェブページを作成し,http://www.naruto-u.ac.jp/journal/info-edu/から公開した。この中には「曽根,林,菊地:電子フォームを用いた申請処理の効率化, vol.5, pp23-28」があり,帳票を数多く取扱う事務においても参考になる内容を公開できた。そのほか,情報認証基盤の構築に向けた情報収集を行った。
最終更新日:2010年02月17日